くず屋の清兵衛はある日、千代田卜斎という浪人から古びた仏像を二百文で引き取り、高木三太夫という若侍に三百文で売った。三太夫がその仏像を磨いていると中から五十両の小判が出てきてびっくり。
三太夫は翌日、清兵衛の元へ五十両を持っていく。「それがしは小判ではなく、仏像を買い求めたのであるから、この小判を受け取るわけには参らぬ」とその金を元の持ち主に返すよう清兵衛に言いつけた。
清兵衛は早速、卜斎に事の次第を伝えるが、卜斎は「それがしは仏像一体を丸ごと売ったのであるから、その中にあるものもすべて買い取った相手の者である。」「たまたまその中に小判があったからといって受け取るわけにはいかん。」こちらも受け取りを拒否。
困り果てた清兵衛は知恵者である長屋の大家に相談し、結果、五十両を清兵衛、卜斎、三太夫の三人で分けることにした。ところが、卜斎はそれでは申し訳ないからと、自分が愛用していた茶碗を三太夫へ譲ると申し出た。一見すると古びた茶碗で、どう磨いても小判など出てきそうもないので、三太夫も安心してその茶碗を受け取った。
ところがこの茶碗が三太夫の主君の目にとまるところとなった。「ややっ。これは幻の名器、井戸の茶碗に違いない。」と三百両で買い上げられた。驚いた三太夫は再び清兵衛を呼び、卜斎に半分の百五十両を届けさせる。
卜斎は三太夫の正直さに大いに感心する。そして三太夫がまだ独身であることを知って、町でも評判の自分の愛娘を娶ってくれるように頼む。
この願ってもない提案を清兵衛から聴かされた三太夫は、「それがしのようなものが卜斎殿の愛娘をもらってよいものか?」と恐縮すると、清兵衛が「いえいえ、卜斎さんからの是非にとのお話です。それに娘さんはなかなかの美人。磨けばもっと美しくなるに違いありません」。すると三太夫、困った顔をして「いや、磨くのはよそう。また小判が出てくるといけないから。」
落語、「井戸の茶碗」の一席である。
落語には腹を抱えて笑う話。ほろりと涙を誘う話。笑いの中にぞっとする恐ろしさを漂わせた話などがある。この「井戸の茶碗」はほっと心を癒される話だ。なぜほっとさせられるかというと、登場人物が全員正直で欲がないからではなかろうか。
現在ならば、古物業者が2000円で仕入れたものを3000円では売るまい。少なくとも怪しげなお墨付きを付けて5倍の値段をつけるのではないか。小判など出てきたならば、訴訟あるいは傷害事件に発展すること間違いなし。
金がすべての今の世では正直には馬鹿が付き、欲がない者は負け犬と呼ばれる。他人の目をかすめて上手に利益をくすねとる者が勝ち組と呼ばれ、もてはやされる。
しかし金にしか価値を見いだせないものは10万円手に入れると100万円欲しくなる。100万円手に入れると1000万円を望む。金は麻薬のようなもの。得れば得るほどさらに多くを求める。その飽くなき欲求は渇いた喉に塩水を注ぎ込むようなものだ。いくら飲んでも渇きは治まらない。治まるどころかより一層の渇きに苦しむ。物欲の亡者と化すのだ。
野田新総理のどじょう演説で一躍脚光を浴びた相田みつをだが、実は以前から多くのファンがいる。特にここ数年愛読者が急増している。その理由は彼の詩が「井戸の茶碗」のような無欲の幸せ、正直さ、誠実さ、潔さを詩っているからだと思う。世の中が拝金主義にまみれるほど、人は日々の行為と対極にある相田の詩や井戸の茶碗を求めるのかもしれない。


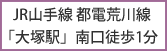


 クリニック西川
クリニック西川