前回のコラムで来年5月から開始される裁判員制度について書き、今回もまた法律に関係したテーマを選びました。これには次のような理由があります。
まず、最近私の担当する患者さんが民事訴訟を起こして、裁判所へ提出する意見書を書く機会が増えてきたことです。さまざまな対人的トラブルを要因として精神的な健康被害を受けることは精神科の診療をしていればごく当たり前に経験するケースです。以前はただその人の治療だけをしていればよかったのですが、最近は相手に対して法的に損害賠償を求める手段をとる方が増えてきたために、裁判資料としての意見書を書くことも仕事に加わりました。日本も段々とアメリカ型の訴訟社会に変化しつつあることを実感します。
2番目には、その流れの中で医療行為に当たっていると、いつ何時医療裁判の被告席に座らされるか分からなくなりました。善意で診療したというだけでは許されない世の中になってきたのです。福島の産科医が、今の医学水準からいって適正な医療行為をしたと思われるのに、不幸な結果に終ったという理由から警察に逮捕されて、刑事訴追を受けるという異常事態にまで到っています。
第3には、成年後見制度が活用されるようになって、刑事訴訟や民事訴訟の際に求められる鑑定に比べればはるかに簡単な家事審判上の鑑定ではありますが、「精神鑑定業務」というものに携わるようになったことです。
第4の理由は、裁判員制度に関して勉強していて、これまでは一開業医である自分とは無縁なことと思っていた刑事訴訟における精神鑑定も、現実的な課題になる可能性があることを知ったことです。
また、私の長男が法曹を志す決心をして、家庭の中で法律に関する話題が自然に増えたことも影響しています。
以上の理由から法に対して関心を深めるようになりました。そうして社会事象や自分の身の回りを見直して見ますと、重大な事件に限らず、今まで何気なく営んできた生活全般が、実は法と密接に関係していることを認識しました。法治国家で生活する以上、全ての行為が法の裏付けなしにはあり得ないということを知りました。しかも医療という特殊な職業従事者は殊更、法を理解している必要があります。さらにその中でも精神科はいろいろな意味でより法律と関係が深い診療科であるということも再認識しました。
それにもかかわらず、我が国の精神医学教育では司法精神医学の分野にはあまり力を注いできませんでした。その結果、その分野に精通している精神科医はごく一握りの人に限られています。私を含めて多くの精神科医が司法に疎いというのが現状です。
そこで改めて精神鑑定、中でも刑事精神鑑定というテーマについて考えてみました。
刑事裁判、特に量刑が死刑になる可能性がある重大な事件では、しばしば被疑者あるいは被告人の責任能力の有無やその程度が問題となって検察官、弁護側の双方から精神鑑定が要請されことがあります。鑑定作業には多大な時間(数か月に及ぶ)と労力を必要とします。皆様も宮崎勤やオウム真理教の麻原彰晃の裁判で精神鑑定のために長期間を費やしたことを覚えていらっしゃると思います。
精神鑑定がなぜ重要視されるかというと、鑑定の結果被疑者あるいは被告人が心神喪失であったと認められれば、犯罪自体が成立しなくなります。犯罪が成立しないわけですから、その人に刑罰を与えることはできません。無罪になります。被告人が心神耗弱であったと認められると、犯罪は成立して被告人に刑罰は与えられますが、量刑は大幅に軽減されます。
最近の風潮はマスコミ、特にテレビのワイドショーによる世論誘導によって「目には目を、歯には歯を」という古代のハンムラビ法典1や旧約聖書2などに見られる同害報復的な考え方に流れています。「殺人などの重大な行為をしたにもかかわらず、無罪にするということは許せない」という考え方が世論になりつつあります。
しかし、こういう考え方の行く先は「仇討」「リンチ」であって、すべての物事を法の支配のもとにおくという近代法治国家の根本原則を揺るがすことになります。感情論に流されず、法律に則って正しい判断をしなければなりません。
ではなぜ違法な行為をしたにもかかわらず、無罪になったり刑が減軽されたりすることが可能になるのでしょう。そもそも犯罪というものが成立してその罪を問うためには次の4つの要件が満たされなければなりません。
1. 犯人の行為
2. 被害としての結果
3. 犯人の行為と被害の結果に因果関係があること
4. 犯人に結果を生じさせようとする意思(犯罪意識)がある
この4つのうち一つでも欠けていれば犯罪として成立しません。
当たり前と思われるかもしれませんが、実際の事件をこの4つの要件ごとに厳密に吟味しますと、この段階で判断に苦しむ例も少なくありません。このことについては今回は省略させていただきます。
ある行為が以上の4つの要件を満たせば、その行為は犯罪として処罰されることになりますが、例外的な事情によって犯罪の成立が否定される場合があり、犯罪成立の「阻却」と言います。阻却される根拠となる例外的な事情を「阻却事由」と呼びます。
この阻却事由にはその行為が通常犯罪とされ禁止されている行為であっても、特にそれを許す法の規定がある場合にはその禁止が解かれる「違法性阻却事由」と、法的な責任を負う能力がなかったり、違法である事を知ることが不可能であったりして責任を問うことができない「責任阻却事由」とがあります。
医師は他人の身体をメスで切開したり、注射で針を刺して血液を抜いたりします。普通ならば傷害罪(刑法204条)に当たる行為を日常的に行っているにもかかわらず、処罰されません。医師による医療行為が犯罪とされないのは違法性阻却事由によるものです。根拠としては刑法第35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」があげられますが、医師法などの法令の中に明確に規定されているわけではありません。このように曖昧さを残しているため、先ほど述べた福島県産科医師逮捕のように、医療の結果次第で不当な司法介入を許す余地を残しているのではないかと思います。
もう一つの阻却事由である責任阻却事由の代表が、自分で行った行為について責任を負うことができる能力がないこと、すなわち責任無能力です。刑法39条1項に「心神喪失者の行為は、罰しない。」と定めてあります。
心神喪失とは精神の障害のために、行為が違法であると認識して、その認識に従って自分の行動をコントロールする能力がない状態を言います。つまり事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)がないか、または弁識能力はあってもそれに従って行動を制御する能力(行動制御能力)が失われた状態です。
また、事理弁識能力または行動制御能力が失われてはいなくても、著しく減退した状態を心神耗弱とよび、犯罪の成立を阻却する事由にはなりませんが、刑を減軽することになります(刑法第39条2項)。心神耗弱は責任減少事由とされているのです。
私が実際に身近に経験した出来事では、脳外科の手術を受けた後の患者さんが、意識がもうろうとした状況で同室の患者さんを果物ナイフで刺してしまったという事件があります。加害者の患者さんは自分の行為を全く記憶していません。病院に対して管理責任を問うことはできても、この方に傷害の罪を問うことはできないでしょう。このように責任能力の観点から犯罪の成立や量刑を考慮しなければならない事例があるのです。
さて、刑事事件において要請される刑事精神鑑定には刑事訴訟法によって、裁判所の命じる公判鑑定と検察官の判断によって行われる起訴前鑑定とがあります。公判鑑定は起訴後の被告人を対象とした精神鑑定で、起訴前鑑定は起訴前の被疑者を対象とした精神鑑定です。さらに起訴前鑑定は嘱託鑑定と簡易鑑定とがあります。この3種類の精神鑑定について簡単に説明をします。
公判鑑定:裁判官の命令で公判の過程で実施されます。一般的には検察官からではなく、弁護人からの要請を受けて裁判所が命令するという形で行われます。検察官は取り調べの段階で被疑者の責任能力ありと判断して起訴するわけですから検察官からの要請ということは異例なことです。鑑定人は裁判所に召喚され出頭し、起立した上で宣誓を行わなければならない。また、鑑定人は証人として扱われるので、証言の義務を負って、場合によっては証人として喚問されて尋問を受けることがあります。その場合、陳述に虚偽があった場合には偽証罪に問われることになります。このために、進んでこの鑑定業務を引き受けたいと思う精神科医は多くはありません。
起訴前嘱託鑑定:被疑者の同意なしに、検察官の判断で実施される精神鑑定ですが、裁判官の許可が必要で、実際の鑑定業務は公判鑑定とほとんど同じくらいの労力を要求されます。ただし、法的には嘱託鑑定を依頼された者は正式には「検察官の依頼/嘱託による鑑定受託者」と呼ばれ、宣誓の義務はなく、鑑定書は検察官に提出します。ただし、裁判所から鑑定処分許可状が発行されて、要求があれば法廷に出頭して証人喚問されることがあります。
簡易鑑定:検察官は逮捕した被疑者を最長23日間勾留することができます。その間に捜査結果に基づいて起訴するか否かの決定をしなければなりません。この勾留中に検察官の判断で実施される精神鑑定を簡易鑑定と言います。この鑑定には裁判官の許可はいりませんが被疑者の同意が必要です。23日間という拘留期間中に鑑定書を提出しなければならないために診察は通常1回で所要時間も1~3時間程度しかかけられません。わが国では、他の二つの鑑定に比べてこの簡易鑑定の数が非常に多いと言われています。この鑑定で責任能力欠如とされた場合には概ね不起訴となります。しかし、責任能力を認めて、検察が起訴に踏み切った場合には、公判において証人尋問を受ける可能性はあります。
いずれの精神鑑定においても要求される主要な課題は「責任能力の判定」です。この責任能力の判定をめぐって司法精神医学では二つの立場があります。それは「不可知論」と「可知論」です。
「不可知論」は精神障害は人の意志や行動の決定過程にどのように影響するのかを厳密に判定することはできないとする立場です。この立場に立てば、狭義の精神病の診断が下れば自動的に責任無能力とします。一方、「可知論」では精神医学的な診断だけではなく、個々の事例の症状の質や程度、またそれらと行為との因果関係について検討すれば責任能力の程度を判定できると考えます。
従来、日本の司法精神医学関係者の間では、「不可知論」を支持する見解が強かったのですが、向精神薬による治療が可能になり、早期に社会復帰できるようになって、精神病から不治の病というイメージが払拭されてきました。それと並行して精神障害者の責任能力に対する考え方は「可知論」に傾いてきました。
もっとも、裁判所は精神鑑定の結果をそのまま採用するわけではありません。精神鑑定の結果はあくまで司法判断をするための一つの材料であり、最終的な判断を下すのは裁判所であることは言うまでもありません。
我が国の判例の歴史を見ますと、裁判所は戦前から精神障害=心神喪失という不可知論は採用していなかったようです。戦後、不可知論的な判例が多発した時期があったようですが、1984年(昭和59年)最高裁判所第3小法廷における大量殺人を起こした統合失調症者の判決で「被告人が犯行当時精神分裂病を罹患していたからといって、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあったとされるものではなく、その責任能力の有・無程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様を総合して判定すべきである。」と判示して、可知論的な判断を採用するべきだと明言し、これ以降の司法判断の立場を決定しました。
したがって、鑑定人を受けた精神科医は、単に精神障害の診断を下すだけではなく、犯行前、犯行時、犯行後を通して可知論的な立場から厳密に弁識能力と制御能力を検討する必要があります。
さて、裁判員制度が開始されますと、前回のコラムで書きましたように、公判前整理手続きの段階で鑑定を請求されるケースが増加すると思われます。現在鑑定業務を担っている数少ない精神科医だけでは要求に応じきれなくなり、私たちのような一般の精神科医にまで要請がくる可能性があります。
一方で、できる限り短期間で鑑定書を作成することが要求されます。さらに、一般市民にも分かりやすい、平易で簡潔な鑑定書でなければなりません。
つい最近、最高裁は裁判の長期化を防ぐ目的から、原則として、鑑定は公判に入ってからは行わないようにするほか、鑑定結果が裁判員の判断に必要以上の影響を与えるのを避けるため、責任能力の有無などの結論には踏み込まないように求めるとの方針を発表しました。また、起訴前に検察側が2~3か月かけて公判前鑑定を行った場合は、弁護側から問題が指摘されない限り、起訴後に新たな鑑定を行わないとの方針も打ち出しました。
来年5月に裁判員制度が実際に開始されたのちに、私たち精神科医がどの程度の影響を受けるのかはいまだ不明確です。しかし、どのような状況になっても対応できるように、日ごろから責任能力という側面に留意しながら診療にあたることを心がけたいと思っています。


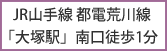


 クリニック西川
クリニック西川