2008年の小柴昌俊先生に続き、今年、梶田隆章先生がニュートリノに関する研究業績でノーベル物理学賞を受賞された。今やニュートリノは我が国のお家芸になったと言えなくもない。だが、ノーベル賞、ニュートリノと大騒ぎしているものの、そもそもニュートリノとはいったいどういう代物なのだろう。
私のコラムではしばしば宇宙の事や素粒子の話をしてきた。ニュートリノについても触れたことがあるのだが、日常生活とかなりかけ離れた分野でなじみが薄いので、多分もうお忘れになってしまったと思う。そこでまず、素粒子とは何ぞやというところから再度お話する。
「素粒子」とは物質を細かく砕いていって、最終的に到達する「それ以上分けることができない最小の粒」のこと。机もパンも私たちの体も、まずは「分子」という小さな粒の集合体だ。しかし分子をよく見ると直径10-10mの「原子」というさらに小さい粒の集合であることが分かった。昔は原子こそ物質の最小単位だと思われていたのだが、更に詳しく調べると原子は「原子核」という直径10-15mくらいのさらに小さな粒の回りを、この原子核よりもさらに小さな、直径10-19m未満の「電子」が飛び回っている構造だと言うことが分かった。
ここで原子核と電子の大きさには10000倍もの差があることが分かるだろう。そんな桁が違う粒がどちらも素粒子だとは考えにくい。その通り、電子は素粒子なのだが原子核はさらに電気的にプラスの陽子と電荷をもたない中性子の組み合わせでできていて、更に陽子や中性子はクォークと呼ばれる粒が3つ組み合わさってできていることが分かった。クォークの大きさも電子と同じく10-19mであり、これこそがこれ以上分解できない素粒子であることが分かった。
電子の直径は実際に測ることはできないのでさまざまな実験から推測しているのであって10-19mという数字は考えられる最大の場合の値で、実際にはもっともっと小さく、限りなくゼロに近い大きさと考えられる。
こんな数字を見せられても想像できないので、原子の大きさを地球に置き換えてみると原子核は野球場程度の大きさになる。そして電子は野球のボールよりも小さい粒になるのだ。さらに一つの野球場と思われていた建物も実はクォークという3つのボールが飛び交う空間でしかなく、それ以外の場所はすべて真空(真空管のように空気がないと言う意味の真空ではなく、本当に何もないただの空間)。
つまり直径10-10mの原子とは言っても実際に存在するのは数個の10-19mほどの素粒子だけでほとんどが何もない空間なのだ。ということは私たちの身体であろうが鉄の塊であろうが、原子の集合体であるすべての物体も実はスカスカの空間ということになる。
と言うことは、空間的な大きさだけから言ったら私たちはいとも簡単に鉄筋の壁をすり抜けられることになるのだが、そういかないのは各原子の回りをがっちりと覆って飛び交っている電子の持つ電磁気力。この電子同士の反発力によって跳ね返されてしまう。だから絶対に壁に突入しようなどと思わないでほしい。全身打撲で大変なことになる。この辺りの感覚が呑み込めないと素粒子の世界は全く理解不能になる。
その後の研究で、陽子や中性子を作るクォークはアップクォーク、ダウンクォーク、チャームクォーク、ストレンジクォーク、トップクォーク、ボトムクォークの6種類あることが分かった。ところで当初、クォークは3種類存在すると思われていた。そこへ、さらに3種類、計6種類あると理論的に予言したのが2008年にノーベル物理学賞を受賞した小林誠先生と益川敏英先生なのだ。
陽子や中性子を形作る素粒子のクォークが6種類あるのに、それに対応して原子を構成する電子は1種類しかないのだろうか。いや電子の仲間も6種類あったのだ。
まずは1937年に、宇宙から飛来する宇宙線の中に電子と同じマイナスに荷電しているが質量が電子の210倍のミュー粒子が発見された。次いで1975年に加速器実験から電子と同じマイナス荷電しているが質量がなんと電子の3500倍もあるタウ粒子が発見された。
一方、放射性物質はその中の中性子の一つが陽子に変って、その際に高速の電子(ベータ線)を放出するベータ崩壊という現象を起こす。この現象を詳しく解析すると物理学の常識である「エネルギー保存則」が成立しないという奇妙な事実が知られていた。つまり、崩壊後の陽子と中性子と飛び出していった電子のエネルギーを足しても崩壊前のエネルギーに足りないのだ。
この現象に対して「パウリの排他律」で有名なヴォルフガング・パウリは、ベータ崩壊では実際には検出器で検知できない未知の素粒子が電子と同時に放出されているのであって、エネルギー保存則は成立しているのだとして、ニュートリノという未知の素粒子の存在を予言した。
しかし、ニュートリノの存在を予言したパウリ自身はニュートリノの検出は不可能だと考えていた。その理由は、ニュートリノは電子と同じくらい小さな素粒子である上に、電気的に中性で、クォークを結び付けている強い力の影響も受けない。弱い力というミクロの世界でしか現れない力でしか他の素粒子と相互作用を起こさない。その弱い力は10-1 8m程度にまで接近しないと力を発揮しないので大部分のニュートリノはすべての物質を通り抜けてしまうからなのだ。
その後の研究で、計算上、地球では1秒間に1cm2当たり660億個ものニュートリノが太陽から降り注いで、私たちの体、そして地球を通り抜けて反対側の宇宙へと通過していると考えられる。それでも私たちは何も感じることができず、地球にもなんの影響ももたらしていない。
そんなニュートリノを実際に検出したのが小柴先生のカミオカンデによる実験だった。大量の水の中をニュートリノが通過する時に、ごくまれに水の電子と衝突することがある。そうするとチェレンコフ光という光を発する。それを高感度の光電子倍増管で検知したのだ。
また、電子の仲間にミュー粒子タウ粒子があると述べたが、ニュートリノも電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3種類の仲間があることが分かった。つまり電子・ニュートリノの仲間もクォークと同様に6種類が揃った。
さて、先に述べた通り電子、ミュー粒子、タウ粒子にはそれぞれ異なった質量がある。ところがなんでもすり抜けてしまうニュートリノの仲間には質量がないと思われていた。だが、スーパーカミオカンデを使った、より精密なニュートリノの検出によって、一つのニュートリノが実は3種類のニュートリノに姿を変えながら飛行していることが分かった(ニュートリノ振動)。これが故戸塚洋二先生と梶田先生の偉業である。
ここから先は難しすぎてうまく説明できないが、振動する(姿を変える)ということはその素粒子が質量を持っていないと起こらない現象なのだ。したがって梶田先生たちの観測結果はニュートリノが重さをもった素粒子であることを証明したことになる。
ニュートリノが質量を持つことが確定したことによって、ダークマターの正体が突き止められるかもしれないとして、宇宙物理学の世界はおおいに色めきだった。
1933年スイスの天文学者フリッツ・ツビッキーが地球から3.2億光年離れた、かみのけ座銀河団内の銀河の動きを詳しく観察した結果、銀河団には観測しうる物質以上の質量があることを発見した。
ダークマター(暗黒物質)と名付けられたこの見えない物質は、その後の研究で、宇宙の中で目に見える物質の5倍も存在することが分かった。言い換えれば、私たちの体を作っているような目に見える物質(クォークや電子などの素粒子で出来ている物質)は全宇宙の質量の20%にも満たないのだ。
そこで宇宙の物質の大部分といえるダークマターの正体が関心の的となっていた。「ニュートリノに重さがある」の報は、ニュートリノをダークマターの最有力候補へと押し上げたのだ。
だが残念なことに電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノそれぞれの正確な質量は未だに不明なのだが、ただこれまでの研究から極めて軽い素粒子であることだけは確実になった。だから、ニュートリノをいくらかき集めてもダークマターに相当する質量を生み出すことはできない。ダークマターは依然として謎の物質のままだ。
また、2011年国際研究チームが「ニュートリノが光速より速く飛ぶ」という報告をして、世界中が大騒ぎになった。何せ光速よりも早く飛ぶ素粒子があるとなると、現代物理学の基礎をなしているアインシュタインの「特殊相対性理論」が否定されることになるからだ。
だが、こちらも残念なことに、後の検証で実験装置の不備による誤報であることが判明した。特殊相対性理論未だ健在。
触ることも見ることもできないのに何かとお騒がせのニュートリノである。


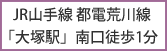


 クリニック西川
クリニック西川